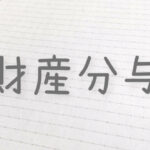
相続と遺贈の違い~遺言書の作成時に知っておきたいこと
遺言書を作成するうえで「相続」と「遺贈」の違いについて理解しておく必要があります。相続とは、亡くなった人が所有していた財産上の権利や義務などを法定相続人に移転することをいい、遺贈とは、遺言によって、所有している財産を無償で譲ることをいいます。遺贈は、誰に対しても行うことが可能で、個人はもちろん、団体であっても譲ることができます。したがって、推定相続人以外の人に財産を渡したい場合には、遺言書に「○○を××(住所:○○市〇〇町5-6-7 生年月日:昭和〇年〇月〇日)に遺贈する」としか書記載できませんが、推定相続人に財産を渡したい場合には、遺言書に「○○を××(住所:○○市〇〇町5-6-7 生年月日:昭和〇年〇月〇日)に相続する」又は「○○を××(住所:○○市〇〇町5-6-7 生年月日:昭和〇年〇月〇日)に遺贈する」と記載できます。すなわち、法定相続人以外には遺言書に「遺贈する」としか書けませんが、法定相続人には遺言書に「相続する」又は「遺贈する」と書けます。




