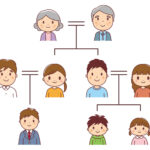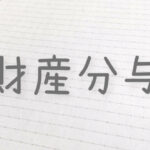相続放棄、財産放棄(遺産放棄)、相続分放棄、相続分の譲渡とは?それぞれの違い、メリット・デメリット
相続が始まると、相続人は被相続人(亡くなった方)の財産について、「相続するか」または「相続しない」のいずれかを選ぶことになります。相続するにも単純承認と限定承認が、相続しない方法にも、相続放棄、財産放棄(遺産放棄)、相続分放棄、相続分の譲渡といった方法があります。ここでは、単純承認、限定承認、相続放棄、財産放棄(遺産放棄)、相続分放棄、相続分の譲渡のそれぞれがどういったものか、それぞれのメリット・デメリット、どういった場合にどの方法を選択すべきかなどを紹介します。