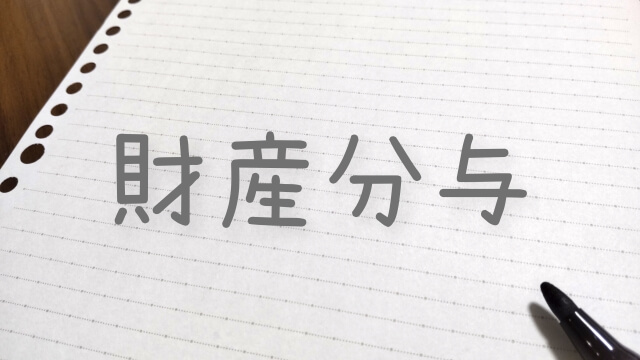遺言書の作成時に知っておきたい相続と遺贈の違い
遺言書を作成するうえで、「相続」と「遺贈」の違いについて理解しておく必要があります。
相続と遺贈の違い
遺言書を作成する際には「相続」と「遺贈」の違いについて理解しておく必要があります。
「相続」とは、亡くなった人が所有していた財産上の権利や義務などを法定相続人に移転することをいいます。「相続」による財産の移転は法定相続人以外にはできません。
一方、「遺贈」とは、遺言によって、所有している財産を無償で譲ることをいいます。「遺贈」による財産の移転は、誰に対しても行うことができ、個人はもちろん、団体であっても移転することができます。
したがって、推定相続人(法定相続人)以外の人に財産を渡したい場合には、遺言書に「○○を××(住所:○○市〇〇町5-6-7 生年月日:昭和〇年〇月〇日)に遺贈する」としか記載できず、「○○を××(住所:○○市〇〇町5-6-7 生年月日:昭和〇年〇月〇日)に相続させる」とは記載できません。
しかし、推定相続人(法定相続人)に財産を渡したい場合には、遺言書に「○○を××(住所:○○市〇〇町5-6-7 生年月日:昭和〇年〇月〇日)に相続させる」又は「○○を××(住所:○○市〇〇町5-6-7 生年月日:昭和〇年〇月〇日)に遺贈する」と記載できます。
すなわち、法定相続人以外には遺言書に「遺贈する」としか書けませんが、法定相続人には遺言書に「相続させる」又は「遺贈する」と書けます。
推定相続人(法定相続人)に「遺贈する」旨の遺言は要注意
遺言書で推定相続人(法定相続人)に財産を移転する場合、「相続させる」「遺贈する」のいずれの記載もできますが、推定相続人に「遺贈する」旨の遺言を残した場合、遺産の種類によって、相続人の遺産の引継ぎが困難となるケースがあります。
(1)遺産が不動産の場合
「相続させる」と「遺贈する」で不動産の移転登記手続きについて違いが出てきます。
推定相続人(法定相続人)に対して「不動産を相続させる」旨の記載であれば、その推定相続人(法定相続人)が単独で不動産の所有権移転登記を行うことができます。
しかし、不動産に関する遺言で、推定相続人(法定相続人)に対して「遺贈する」旨の記載であった場合、他の相続人とともに、不動産の所有権移転登記をする必要があります。
そのため、遺言内容に不満がある相続人がいると、不動産の所有権移転登記が困難になるケースがあります。
【例文サンプル】
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の土地を、妻○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。
記
所在 ○○市○○町○○丁目
地番 ○○番○○
地目 宅地
地積 ○○平方メートル
(2)遺産が借地権・借家権の場合
借地権・借家権に関する遺言で、推定相続人(法定相続人)に対して「相続させる」旨の記載であれば賃貸人の承諾は不要ですが、「遺贈する」旨の記載である場合は、遺産を引継ぐには賃貸人の承諾が必要になります。
【例文サンプル】
第○条 遺言者は、遺言者が有する下記の建物及び借地権を、妻○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。
記
1 建物
所在 ○○区△△1丁目
家屋番号 2番10
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 ○○.○○平方メートル
2階 ○○.○○平方メートル
2 借地権
上記建物の敷地である○○区△△1丁目2番10、宅地○○平方メートルに対する借地権
賃貸人 ××(○○区△△2丁目2番10)
(3)遺産が農地の場合
遺言によって推定相続人に農地を取得させたい場合、「遺贈する」旨記載すると、農地法による農業委員会又は都道府県知事の許可が必要となります。
この場合、推定相続人が農業に従事していない場合など、許可が下りず、農地の登記ができない可能性があります。
一方、「相続させる」旨を記載した遺言であれば、農地法による許可は不要であるため、スムーズに農地を取得させることができます。
推定相続人(法定相続人)に対して遺産を与える内容の遺言であれば「相続させる」と記載するようにしましょう。
包括遺贈と特定遺贈
遺言によって財産の遺贈をする場合、包括遺贈と特定遺贈という方法があります。
包括遺贈とは、遺産の全部・全体に対する配分割合を示して遺贈することをいいます。
一方、特定遺贈とは、遺産のうち、特定の財産を特定の人に遺贈する旨記すことをいいます。
【包括遺贈の例文サンプル】
・第〇条 遺言者は、全財産の3分の1を孫〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に遺贈する。
・第〇条 遺言者は、全財産を孫〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に包括して遺贈する。
【特定遺贈の例文サンプル】
・第〇条 遺言者は、株式会社××の株式を、△△(平成〇年〇月〇日生)に遺贈する。
・第〇条 遺言者は、別紙財産目録〇記載の不動産を、△△(平成〇年〇月〇日生)に遺贈する。
包括遺贈の場合、その割合に基づいた遺産分割が必要になります。
不動産など分割が難しい財産が含まれるケースがあるため、相続時または相続後にトラブルに発展する可能性があります。
そのため、トラブルを予防するためにも、特定遺贈の方法で、それぞれの財産の帰属先を明記しておいたほうがいいでしょう。
なお、法定相続人は遺贈に対し原則として遺留分に関する部分のみ反対することができます。
遺言書を作成しても油断は禁物
遺言書は、相続対策として身近であり、有効な対策の一つです。
ただし、遺言書を作ったからといって油断は禁物です。
特に、相続人以外の人に遺贈をする旨の遺言を作成したとき、相続人や遺贈を受ける人(以下、「受遺者」といいます)がそのことを知らされていない場合には、遺言者の相続発生後、相続人の間や受遺者との間でトラブルとなる可能性があります。
相続対策において、生前に推定相続人や受遺者となる人ときちんとコミュニケーションを取っておくことが非常に重要となります。
生前に遺言書の内容をすべて明かす必要はありませんが、遺言書を作ったことや誰に財産を遺したいかといったことを、伝えておくことも相続対策につながります。
(相続人は要注意)
受遺者が遺贈のことを知らされておらず、相続人以外の執行者がいない場合、相続人が遺言書を破棄して勝手に相続してしまうケースも考えられます。
しかし、遺言書の破棄は、相続欠格にあたり、相続人としての権利を失いますので注意が必要です。
遺言書に似ている死因贈与
遺言書に似ている相続対策として死因贈与というものがあります。
遺言書は、遺言者の一方的な意思表示で成立します。一方、死因贈与は贈与契約の一つであるため、贈与をする人と受ける人の意思表示がなければ成立しません。
また遺贈を受ける受遺者は他の相続人との関係などから遺贈を辞退することもできます。
したがって、生前に遺産を渡したい人の承諾を得ておきたい場合には、死因贈与契約を締結することも一つの選択肢です。
死因贈与は、遺言書の規定を準用しているものが多いため、贈与税ではなく、相続税の課税対象になります。